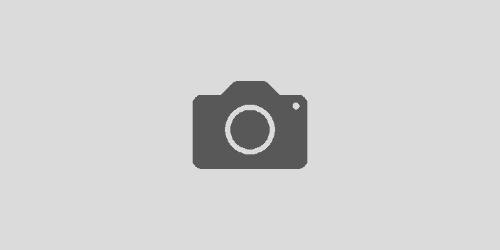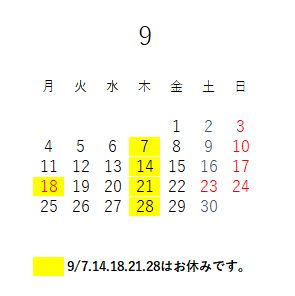不眠のタイプと特徴を把握し、睡眠をコントロールする。
私もなかなか寝付けない時があります。ひどかったのは、新型コロナウィルス新規感染者が多くなり、初めて緊急事態宣言が発令された頃。今思い返せば「心脾両虚」という状況でした。睡魔がきても寝れない。しかも動悸がすごく、何を考えているのかわからなくなっていました。様々な方法で何とか寝ようと思っても効果が出ず、睡眠薬に頼ろうかとも思いました。
こんな時、出ている症状だけを追いかけていて、ネットなども調べていた時期もありました。これって西洋的な考えですね。漢方を勉強をしていたのに。視野が狭かったです。
- 入眠障害。(なかなか眠れない。)
- 熟眠障害。(夢が多く、ぐっすり眠れない。)
- 中途覚醒。(眠れてもすぐに目が覚めてしまう。)
西洋的な考えでも、不眠に対してタイプがあります。しかし、症状だけで、「何故そうなるのか。」がわかりにくいです。なので、「何故」に悩んでしまいがちに。
漢方では「神安則寝、神不安則不寝」という言葉があります。「神」というのは「神明」の事を指し、精神や意識、思考などを言います。レントゲンなど西洋医療が発達する以前から、人間を観察し、不調はどうして起こるのかを見てきました。この「何故」を俯瞰的に見ることにより、心のコントロールができ、不眠に悩む方が一人でも少なくなれば嬉しいと思い、このブログを書きました。
では、これから漢方で考える不眠のタイプをお伝えしますね。
不眠のタイプを解消法
①心脾両虚
ストレスや考え過ぎが続き、脳に過度な負担をかかると、「心」と「脾」の両方のエネルギーが下がる時があります。これが「心脾両虚」。
漢方で「脾」は食べ物を消化吸収し、「気」「血」などのエネルギーを作り、全身を運ぶ役割。そして、血液が血管から漏れ出さないようにする作用があらります。「心」は精神活動も司ります。
「脾」が弱まり、「心」に充分なエネルギー供給ができないと、精神活動が不安定になります。

この様な状態になると、
などが起こりやすくなります。
- 眠いのに寝れない。
- 眠りが浅い。
- 動悸。
- 不安感。
- めまい。
- 健忘。
- 貧血。
- 不正出血。
- 食欲不振。
漢方薬だと、加味帰脾湯などがオススメになります。
日常での改善ポイントとしては、胃腸に負担がかかっているので、よく噛んで食べる。そして、消化にいいものを食べましょう。食材は芋類、豆類。南瓜、百合根、蓮根。赤色の食材(辛くない物)もオススメです。
体が疲れている為、激しい運動はオススメしません。ストレッチなど、ゆったりとやりましょう。
②肝火上炎
漢方では、「気」の巡りをよくするのは「肝」。「肝の疏泄作用」といいます。
「肝」は「春」や「怒りの感情」に影響を受けやすいとされます。そして、緊張やストレスなどがかかると「肝」の気が滞る「肝気鬱結」という状態になります。
この状態から、過度な怒りやストレス、油っこい食べ物やお酒・刺激の取り過ぎなどをしてしまうと、「肝」に熱をおび、「肝火上炎」という状態になります。

この様な状態になると、
- イライラして寝れない。
- 目がさえて寝れない。
- 顔色が赤い。
- 目の充血。耳鳴り。
- 口内炎。鼻血。
- 胸・脇腹が熱っぽく痛い。
- 便秘。
- 尿が黄色。
などが起こりやすくなります。
漢方薬だと、柴胡加竜骨牡蛎湯などがオススメになります。
「肝火上炎」は「肝」に熱をもっている状態。まずはリラックスを心がける。深呼吸をして落ち着くことが大事。
食べ物などでは、できるだけ、飲酒や刺激物。油っこいもの。甘い物を控えましょう。
③肝血虚
漢方では、「肝」は「疏泄作用」の他に、「血」を貯蔵する「蔵血作用」をするといわれます。
眠るためにもある程度の力が必要とされています。過労や慢性疾患、慢性出血などで必要な力が不足すると起きやすいタイプです。
「肝」は「春」に影響を受けやすいとされます。過労が続くと「肝」の血が足りない「肝血虚」という状態になります。

この様な状態になると、
- 眠いけど寝れない。
- 夢を多く見る。
- 顔色が白くツヤがない。
- 視力低下。目のかすみ。
- 爪が割れやすい。
- 髪がパサつく。
- 月経量減少
- めまい。動悸。
- こむらがえり。
などが起こりやすくなります。
漢方薬だと、酸棗仁湯などがオススメになります。
「肝血虚」は「肝」に血が足りない状態。血を養う食材として、にんじん、ほうれん草、小松菜、クコの実、ぶどう、イカ、タコ、落花生などがオススメ。
④心腎不交
加齢とともに睡眠時間が少なくなる。だるさやほてりをともなう不眠があります。
漢方では、「心」と「腎」は常に影響しあうと考えています。
心は火、腎は水の役割を持ちます。互いに、燃えすぎず冷えすぎず、水浸しにならず乾きすぎずの状態を保っています。この状態を「心腎相交」といいます。
この均衡が乱れた状態が、「心腎不交」です。火が盛んな状態と乾いた状態を同時に出てきます。
悩みすぎたり、考えすぎたり。慢性疾患、加齢や房事不摂生などで腎陰が消耗し、心陽が抑えられなくて起きます。

この様な状態になると、
- 眠れない。
- すぐに目が覚める。
- 足腰がだるい。
- 手足などがほてる。
- ふらつく。
- 喉が乾く。
- 寝汗。
などが起こりやすくなります。
漢方薬だと、六味地黄丸などがオススメになります。
オススメ食材は
- 体の熱をとる食材として、きゅうり、トマト、冬瓜、もやしなど。
- 「腎」を養う食材として、豚肉、牡蠣、黒豆、ゴマ、クコの実など。
辛味食材は控え、体に潤いを与える「酸甘化陰」。酸味と甘味の組み合わせもオススメです。
共通の解消法
オススメは朝にウォーキングをすること。
ウォーキングのように、ある一定リズムで体を動かすと、脳内伝達物質であるセロトニンが生成しやすくなります。そして、このセロトニンが夜になると、睡眠を誘発させるメラトニンとなります。(できない人はストレッチなどをしましょう。)
そして、朝日を浴びると、体内時計がリセットされ、リズムが整います。(※体内時計は1日25時間とされています。脳にある松果体が朝日を感じると、体内時計がリセットされます。)
この時に関係してくるのがブルーライト。虹ってありますよね。人間が目視できる光を「可視光線」と言います。この青く見えるのがブルーライトと呼ばれるもの。太陽のように強い光でのブルーライトを浴びると、メラトニンの生成を止めるため、脳は目覚めてきます。室内のLED(青色LEDを使用しているため)やスマートフォンなどの光でもメラトニン生成を20%カットさせてしまうので、睡眠の阻害となります。
あとは、深部体温が下がる時に眠たくなります。赤ちゃんが眠たい時に手のひらを触ると熱いのは、そこから放熱をし、深部体温を下げているからと言います。では、どうすれば深部体温を下げることができるのか。それは、ゆっくりお風呂に入り、体を温めましょう。
- 朝ウォーキングをする。
- 朝、太陽の光を浴びる。
- 寝る直前にスマホをできるだけ控える。
- ゆっくりお風呂に入る。
上記のタイプ別の対処法と、こちらの方法を組み合わせてやってみてくださいね。
「眠たいけど眠れない!」と思えば思うほど、怒りやストレスがたまり、いっそう寝つきが悪くなります。この時はこちらのブログで書いた瞑想方法などで、気持ちを落ち着かせてくださいね。
私がやっている睡眠法(疲労感は小顔矯正の敵!) | ブログ:進化する小顔矯正。 (tokyo-kogao.com)
「肝火上炎」で「肝」に熱がおびて、カッカして寝れないのに、お酒による「熱」で寝ようと思っても、より、熱がおび、寝れなくなります。
不眠は睡眠をコントロールできていない状態。俯瞰的に、不眠のタイプを把握し、それに合わせた対処法をし、自分をコントロールできてくると、心地よい睡眠導入になります。もし、悩みなどがあり、コントロールできない場合は、「今は考えるのやめた!」と早めな口調で唱えて、「明日いい考えが浮かんで、笑顔で気持ちがいい。」と口角を少し上げて言ってみましょう。胸の辺りが緩んでくる感じがしますよ。寝る前に考えることって、ネガティブ要素が強く、あまりいい考えも浮かびませんしね。それよりも、今日起こったいい出来事や感謝を考えた方が気持ちがいいですよね。
不眠で悩む方が本当に多いです。少しでも眠れるように力になれたら嬉しいです。
振骨小顔センター
大渕